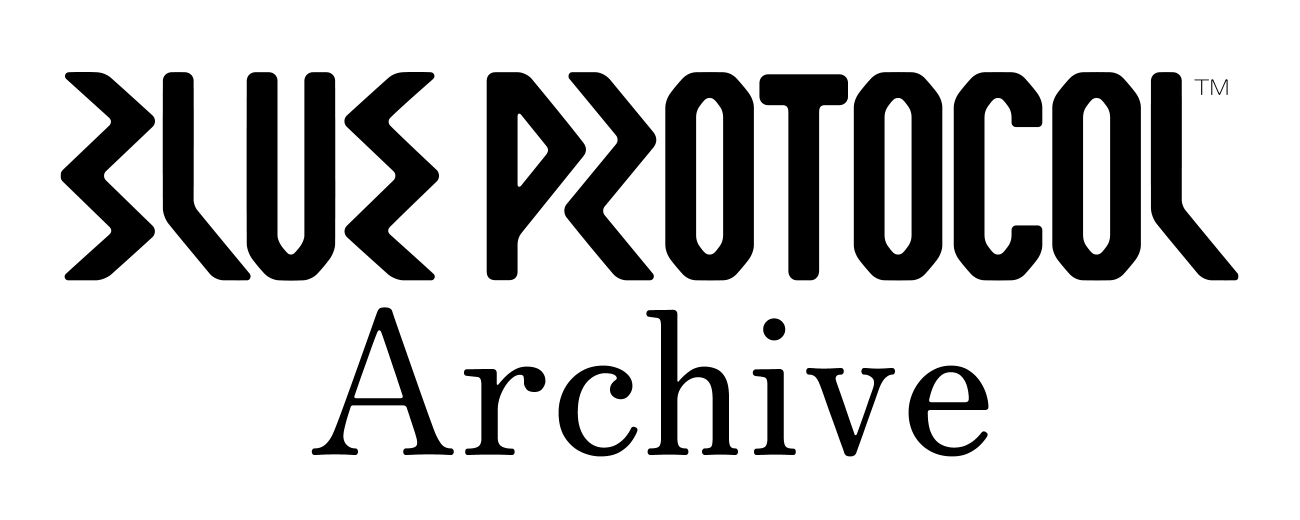察してほしい恋心
uploaded by
サニーブライアン
おたんぬ様主宰のMemory of BLUEPROTOCOL 2に寄稿した作品です
「おおっ。見ろ、下僕よ。花火が上がったぞ」 フェステの言葉に振り仰ぐと、いくつもの煌びやかな大輪の花が夜空を彩っていた。 その花が咲き誇るたびに、周囲から歓声が上がっている。 「開港祭、無事に開催されてよかったね」 「うむ。まったくだの」 私とフェステは顔を見合わせて微笑みあった。 バーンハルト公国で発生したクーデター未遂による混乱や、竜族の暗躍など不穏な状況が続く中、一時は開催を危ぶまれたアステルリーズ開港祭だったけど、市民からの強い要望や関係各所の尽力によって、何とか開催に漕ぎつけることが出来た。 おかげで、一時期は停滞気味だった物流や人の流れも、以前と同じかそれ以上に活発になっていた。 大通りには所狭しと様々な露店が立ち並び、競い合うような客寄せの声が、道行く人々の耳目を楽しませる。冷やかして回るだけでも楽しいくらいだ。 だけど、人と物の動きが激しくなれば、それだけよからぬものが流れ込んでくる可能性も大きくなる。 そこで開拓局は、私達冒険者に治安維持のため、街の巡回依頼を出した。 あらかじめ指定された巡回ポイントを重点的に巡回しつつ、それ以外は自由行動でよいという、比較的おいしい内容の依頼だ。 しかし、有事が発生した場合には、臨機応変な対応が求められるため、依頼を受けられるのは中堅クラス以上の冒険者のみだ。 かく言う私とフェステも、その依頼を受けて祭りを満喫……もとい、巡回している最中だったりする。 「のう、下僕よ。わしは腹が減ったぞ」 「うん。私も」 私達の視線は、ある屋台に釘付けになった。アステルリーズの海で獲れた魚介類の串焼きを提供している店だった。食欲をそそる香ばしい香りが、私達のいる場所まで漂ってきている。 「串焼き屋かぁ」 「わしはエビの串焼きを所望するぞ! 買ってくるのじゃ、下僕!」 「はいはい」 私とフェステは、匂いに誘われるようにして、串焼きの屋台へ向かう。 「へい、らっしゃい!」 ねじり鉢巻きをした屋台の親父さんが、威勢のいい声で出迎えてくれた。 「おやっさん。エビの串焼き二本頂戴」 「毎度!」 早速私とフェステは、購入したエビの串焼きに齧り付いた。 歩きながら物を食べるのは、ちょっと行儀が悪いかもしれないけど、お祭りだし問題ないよね。 程よい塩味とエビ特有の香ばしい磯の風味が口いっぱいに広がるのがたまらない。 「美味いのう! やはり、海産物と言ったら、アステルリーズじゃな!」 「だねえ。一本じゃ足りなかったかも」 名残惜しそうに串を振りながら、私はつぶやいた。 さっきの露店まで戻って、もう一本買おうか真剣に悩んでいると、前方から見知った男女が歩いて来るのが見えた。 「おっ。見ろ、下僕よ。カーヴェインとシャルロットじゃ」 カーヴェインとシャルロットもこちらに気づいたようで、笑顔で手を振りながら駆け寄ってきた。 「やあ、カーヴェインにシャルロット」 「師匠! それに、師匠の主も!」 「二人共こんばんは!」 私とフェステは顔を見合わせ、示し合わせたように口の端を吊り上げた。 「二人共奇遇だねえ。もしかして、デート?」 「ふえっ!」 わかりやすく顔を赤らめ、途端に挙動不審になるシャルロット。 「中々、ねんごろな様子だったぞ?」 そう言ってフェステは、「ぐふふ」と人の悪そうな笑みを浮かべる。 「え、ええっと、その……」 シャルロットは、モジモジしながら、何かを期待するかのようにカーヴェインのほうに、ちらちらと視線を送っている。 「いや、デートでは無いよ」 そんな視線に気づいているのかいないのか、カーヴェインはいつも通り快活に否定した。 シャルロットの顔からスッと表情が消えるのを見て、私は頭を抱えそうになる。 「そ、その割には、随分と仲睦まじい様子だったぞ? なあ、下僕よ!」 慌てたように言い募るフェステに、私はうんうんと頷く。 そんな私達のフォローを知ってか知らずか、カーヴェインは苦笑を浮かべている。 「仲睦まじそう? 別にそんな事は無いですよ。なぁ、シャルロ……」 そこでようやく、カーヴェインは、シャルロットの表情に気付いた。 いつも快活な笑顔を浮かべている彼女の顔が、能面のような無表情になっていたからだ。 理由はわかっていないみたいだけど、自分がとんでもない地雷を踏んだ事だけは理解できたらしい。 「あ、あれ? いったい、どうしたんだ、シャルロット……?」 「…………ううん。別に、何でも?」 たっぷり数十秒間経過した後、シャルロットはいつも通りの笑顔を浮かべた。 いつも通りの笑顔なんだけど、なんというか、こう、言い知れぬ威圧感みたいなのがあって、滅茶苦茶怖い。 カーヴェインもそれは感じたようだけど、理由がわかっていないのか、ただただ困惑しているみたいだ。 「私達、開拓局から巡回の依頼を受けたんだ。それで、二人で回っていたの。うん、そう。ただそれだけなの。断じてデートなんかじゃないわ。間違えないでね?」 「う、うむ。そうなのか……」 「じゃ、じゃあ、私達と同じだね……」 フェステと私は、いたたまれなくなって、目を泳がせながらそう答えるのが精いっぱいだった。 「師匠。俺は、何かシャルロットの機嫌を損ねるような事をしてしまったんだろうか……?」 本気で分かっていなさそうなカーヴェインに、私は少しイラついた。 あまつさえ、自分が被害者面なのが気に入らない。 「えい」 とりあえず、腹が立ったので、カーヴェインの脛を蹴飛ばした。 「痛っ!? な、何するんですか、師匠!」 「そりゃ」 「え、ちょっ!?」 フェステも私と同じ気分だったのか、反対側の脛を蹴りつけた。 「ねえ、二人共。良ければ、一緒に回らない?」 そうやって、カーヴェインの足をフェステと二人でゲシゲシ蹴っていたら、シャルロットがそんな提案をしてきた。 私とフェステは、カーヴェインへの折檻を止め、顔を見合わせた。 私達は、別に構わないんだけど、むしろお邪魔なんじゃないだろうか。 「良いの良いの。私とカーヴェインはただの友達なんだから! そう、友達! 良いよね、カーヴェイン。二人も一緒で!」 「ああ、俺は構わない。むしろ、師匠とその主がいてくれれば心強い!」 ああ。これはダメだ。 力強く同意するカーヴェインに、私とフェステは肺が空になるほどの大きなため息をつくのだった。 * 「ねえ、シャルロット」 私は、前を歩くカーヴェインの背を見つめながら、隣を歩くシャルロットに囁いた。 「カーヴェインとは、あれからどうなの?」 「どうもこうも、見たまんまだよ……」 シャルロットは虚ろな表情で自嘲気味に笑った。その笑みが、とてもいたたまれない。 「まあ、さっきの様子を見る限り、さもありなんと言ったところだのう」 フェステも溜息交じりに肩を竦めている。 さっきのやり取りでそうだろうとは思っていた。思ってはいたが、カーヴェインが照れ隠しで胡麻化しているのではという一縷の望みに期待したのだ。 「長い事、二人っきりで居た期間もあったろうに、何の進展もないというのは、さすがにおかしいのう。も、もしや……」 フェステが何かに気づいてしまったかのように、愕然とした表情になった。 「もしや、カーヴェインには、そっちの趣味が……!!」 「さすがに、それは……」 これまでの付き合いで、そういう兆候は見られなかった。単純に、カーヴェインが朴念仁過ぎるだけだと思いたい。 それを確かめるというわけではないが、今回の依頼は、二人の仲を進展させるまたとない機会だ。 ふと、道端に色とりどりのアクセサリーを販売している露店を見つけた。 ……良いこと思いついた。これは使えるかもしれない。 「ねえ、見て! あんなところに、アクセサリー売ってるお店があるよ!」 ちょっとばかしわざとらしい大声で、私は露店を指さした。 「あ、ほんとだ! すごい、綺麗~!」 「ほほう。これは、中々の品揃えだのう~」 シャルロットは顔を輝かせ、露店に駆け寄った。しゃがみこんで茣蓙の上に並んでいる様々な意匠のアクセサリーに目を輝かせる。 フェステは私の意図を察してくれたらしく、シャルロットの隣で露店の商品に見入っている。 「いらっしゃい、可愛いお嬢ちゃん達」 愛想のよい露店商のおばちゃんは、にこやかに私達を出迎えてくれた。 「か、可愛いだなんて、えへへ……」 「うんうん、可愛いよ、シャルロットは可愛い!」 「うむ! さすが、みんなの歌姫だの!」 私とフェステは、カーヴェインに聞こえるような声で、シャルロットを褒めそやした。 私は所狭しと並んでいるアクセサリーの中から、髪飾りを一つ手に取った。 「ほらほら! この髪飾りなんて、シャルロットによく似合っているよ!」 手に取った髪飾りをシャルロットの頭にかざしつつ、所在無さげなカーヴェインに、いい加減察しろとばかりに視線を送る。 「うむうむ! シャルロットの髪色にピッタリだの!」 「うんうん! よく似合っているよ! お嬢ちゃんの髪に飾られるために作られたみたいだねえ!」 そのやりとりで、私達の関係性を把握したのか、店主のおばちゃんが援護射撃をしてくれた。 「どうだい、彼氏! お安くしとくよ!」 (おばちゃん! ナイスアシスト!) 私は、心の中でおばちゃんに喝采を送った。 フェステと顔を見合わせ、サムアップする。 私達女性陣は、期待のこもった眼差しで、カーヴェインを見つめた。 「彼氏? 違いますよ。俺は彼女の友人ですよ」 一点の淀みもない口調で、最悪の台詞を言い放った。清々しいくらいの朴念仁ぶりだ。 シャルロットの表情が一瞬にして凍り付くが、カーヴェインは全く気付いていない。 「へえ、髪飾りか。確かに、シャルロットによく似合うな」 「ふえっ⁉ そ、そうかな……?」 能面のような表情だったシャルロットが、一瞬で相好を崩した。 シャルロットはシャルロットで、カーヴェインの言動に一喜一憂しすぎだ。チョロすぎる。 頭を抱えそうになる私をよそに、カーヴェインは、髪飾りの一つを手に取った。 おっ! もしかして、『シャルロットにはこっちのほうが似合うよ(キリッ)』とかやるつもり? それはそれで彼氏っぽくて良い! だけど、そんな私の期待はあっけなく裏切られた。 「この髪飾りは、アインレインに似合いそうだな」 「「「「は……?」」」」 私、フェステ、シャルロット、そして店のおばちゃん。四人の声が異口同音にハモった。 「ねえ、カーヴェイン」 シャルロットはカーヴェインに微笑みかける。 やだ。シャルロット嬢、めっちゃ怖い。笑顔がこんなに恐ろしいって感じたのは初めてかも。 そういえば、笑顔って、肉食獣が獲物に襲い掛かるときの表情だっていう話をどこかで聞いたことがあったな。 「どうして、そこで、アインレインの、名前が、出てくるの……?」 わざと文節を区切るような話し方に、シャルロットの怒りと悲しみが、痛いほど見て取れた。 「カーヴェイン。キミには失望したよ……」 「お主という男は……。鈍感もここまで極まれば、ある種の才能かもしれんの」 「兄ちゃん。彼女の前で、他の女の話かい……?」 私達からの失望と軽蔑の入り混じった視線に、カーヴェインは狼狽えているみたいだった。 だけど、その理由は本気でわかっていなさそうだ。 「お、俺は、何か間違ったことを……? アインレインは、神殿に籠りきりで大変だろうから、せめてお土産をと思っただけなんだが……。あ、もちろん、師匠達や、エーリンゼさんやティリスさんにも……」 違う、そうじゃない。この男、何一つとして理解していない。 朴念仁もここまでくると、もはや訴訟レベルだ。 「さて、と」 ついてもいない埃を払い、シャルロットはおもむろに立ち上がった。 「二人共、そろそろ行こっか」 「あー、うん。そうだね。おばちゃん、ごめんね」 「邪魔したの」 「いやいや、良いってことだよ。頑張んなよ、お嬢ちゃん……」 店のおばちゃんに別れを告げ、私達はカーヴェインを放置してさっさと歩き始めた。 「あっ、ちょっ……! みんな待ってくれ!」 カーヴェインが慌てて追いかけてきたが、私達は振り返らなかった。 * 「今度はあっちのほうを巡回してみない?」 「う、うむ。そうだの」 シャルロットの空元気が痛々しい。 さっきの一件依頼、シャルロットは、カーヴェインをまるで空気のように扱っている。 カーヴェインが何か声をかけても、全く反応しない。 カーヴェインは、かなり気まずそうにしているが、こればかりは自業自得だ。 「……下僕」 隣を歩くフェステが、小声で囁いた。 私は軽く頷くと、シャルロットに声をかけた。 「シャルロット。今度は、あっちの方を見て回ろう」 私が指さしたのは、人通りのほとんどない路地裏だ。 「えーっ? あっちは、何もない路地裏だよ?」 「シャルロット。いちおう、私達は巡回してるんだよ? ああいう目立たない場所で悪さしている奴がいないかどうか、チェックしないと」 「あっ!」 「やれやれ。すっかり忘れっておったようだの」 「えへへ……」 フェステが呆れたように頭を振ると、シャルロットはばつが悪そうに笑った。 「カーヴェイン! 何やってんの、早く行くよ!」 私は背後を振り返ると、、カーヴェインに呼びかけた。 「悪い悪い」 「カーヴェイン。気付いている?」 駆け寄って来たカーヴェインに小声で問いかけた。 「ああ、分かっている。さっきの露店のあたりからだ」 カーヴェインは視線を前に向けたまま言った。 「さすがだね」 「あれだけの殺気を放っておいて、気づくなという方が無理だよ」 私が褒めると、カーヴェインはちょっと照れ臭そうに言った。 「えっ? えっ? どういうこと……?」 ただ一人、状況が理解できていなかったらしいシャルロットが目を白黒させている。 「わしら、何者かにつけられてるんじゃ」 「ええー……!」 目を見張り、大声を上げそうになったシャルロットだけど、私が人差し指を立てると、慌てて声を潜めた。 露店を離れたあたりから、私達の様子をうかがう複数の視線を感じていた。その視線には、明らかな殺意が込められていた。 しかも、その殺意の先は、シャルロットに向いていた。 サラムザートでシャルロットを襲った連中の仲間かもしれない。 「無関係の人々を巻き込むのは不味いな」 「うん。だから、あそこの路地裏に誘い込むつもり」 「わかった」 こんな人通りの多いところで切った張ったなんてやりだすわけにはいかない。 あそこなら、誰にも迷惑をかけることは無い。 「カーヴェインは、シャルロットを護って。私とフェステは大丈夫だから」 フェステに視線を向けると「うむ!」と大仰にうなずいた。 「ああ、任せてくれ! シャルロットは、命に代えても俺が護る!」 「い、命に代えても……!?」 こんな時にもかかわらず、シャルロットは顔を赤くしている。 シャルロットはシャルロットでチョロイン気質だけど、何の気なしにこんな台詞を口走っちゃうカーヴェインにも、大いに問題がありそうだ。 私達は、楽しく談笑しているふうを装いながら、路地裏に入り込む。 路地の中ほどまで進んだあたりで、進路をふさぐように、黒ずくめの男達が現れた。振り返ると、退路を塞ぐように、背後からも現れる。 前後から挟み撃ちにされた状態だ。 「カーヴェイン。後ろの奴らをお願い」 「ああ、任せてくれ」 そう言って私は、前方に立ち塞がる黒ずくめ達を見据えた。 「ハッ! 態々、こんな路地裏に入り込んで……」 「おおおりゃあああああ!!」 頭目らしい男が何かを口に仕掛けたところで、私は自慢の大盾を構えて突進した。 悪党の前口上なんぞを律儀に聞いてやるつもりなんか、さらさら無い。 そんなにくっちゃべりたいなら、ブチのめしてふん縛った後、好きなだけしゃべらせてやる。 「おごっ!」「がっ!?」「べっ!?」 進路上の手下を派手に吹き飛ばしながら、私は頭目に肉薄する。 「な、なんなんだ、こいつ! ただの小娘じゃねえ……!!」 「うりゃ!」 「べっ!!」 手下をぶっ飛ばした勢いをそのままに、私は頭目の顔面に大盾を叩きつけてやる。 何かがひしゃげるような鈍い音とともに、頭目はあっけなく目を回した。 「ほっほっほー! 見事じゃ! さすが、わしの下僕じゃ!」 「ちょっとは手伝ってよ、フェステ」 「そ、そんな事より、カーヴェインとシャルロットの加勢に行くのじゃ!」 私達はカーヴェインの加勢に向かうが、結論から言うとその必要はなかった。 閉所では不利なはずの槍を巧みに操り、シャルロットを背に危なげなく立ち回っていた。 槍のリーチを生かした突き技主体の攻撃で、一人また一人と、戦闘不能に追い込んでいく。 「ぐああっ!」 「クソがっ!」 また一人、カーヴェインの槍を受けて崩れ落ちるが、その背後から別の男が飛び出し、カーヴェインに迫る。 「カーヴェイン、危ない!」 私の声に、カーヴェインは即座に槍を引き戻すが、間に合いそうにない。 黒光りする刃がカーヴェインに届くかと思われたその瞬間、シャルロットの放った矢が男を貫いた。 「私だって、戦えるんだから!」 「シャルロット! 助かった!」 仲間の大半を戦闘不能に追い込まれ、残りの黒ずくめ達は、明らかに動揺していた。 「あんた達のボスは、やっつけたよ。まだやる気?」 私は、肩越しに背後で伸びている頭目を指す。 残った黒ずくめ達は、無言で視線を交わすと、音も無く逃げ去って行った。 「これで、状況終了かな?」 「うむうむ。わしらの大勝利じゃな!」 私の言葉に、フェステは鷹揚にうなずいた。 「みんな、怪我は無い?」 「俺は大丈夫だ。シャルロットは?」 「私も大丈夫だよ!」 みんな怪我が無いようで何よりだ。 「ほーっほっほっほ! わしらに掛かれば、造作もない事だの!」 フェステは何もしてないじゃん、とは思ったけど、敢えて口には出さなかった。 最後がちょっとヒヤリとしたけど、まあ、余裕の大勝利と言えるだろう。 「さて。後は、こいつらを開拓局に突き出さないとね」 その後、私達はふん縛った黒ずくめ達を開拓局に突き出し、依頼は無事終了した。 尋問には私達も立ち会ったのだけれど、肝心な事は何一つわからなかった。 黒ずくめ達は、金で雇われただけの連中で、依頼人の素性は一切知らされていなかったみたいだ。 ただひとつ、シャルロットを亡き者にすれば、報酬は思いのままとだけ知らされていたようだ。 「やっぱり、私の命が目当てだったんだ。私、いったい何者なんだろう……。みんなにも迷惑掛けちゃったし……」 シャルロットは、僅かに目を潤ませて俯いている。 私は、カーヴェインの横っ腹を肘で突いた。 反対側からはフェステが、同じようにカーヴェインに肘を入れている。 さすがに、いくらニブチンのカーヴェインでも、今この場で自分がどうすれば良いのかは、察してくれたようだ。 「心配するな、シャルロット。俺達は、これからもずっと君の味方だ」 ……まあ、及第点にしとこうか。本当は、俺達じゃなくて、俺って言ってほしかったんだけどね。 「そうそう、カーヴェインがシャルロットを守ってくれるよ! 心配ないって!」 「うむうむ! 何しろ、カーヴェインはシャルロットの騎士だからのう!」 フェステはニヤリと笑うと、カーヴェインに言った。 「のう、カーヴェイン? 騎士は、一度口に出したことは、絶対に守るんだったのう?」 「ああ、もちろんだ。俺はあの時、シャルロットを護ると誓ったからね」 「カーヴェイン……」 シャルロットは潤んだ瞳で、カーヴェインを見上げた。 「良かったね、シャルロット。カーヴェインが一生護ってくれるってさ!」 「い、一生!?」 「え、ちょ、し、師匠!?」 「うむ! 騎士に二言は無いからの!」 「い、いや! 二人共待ってくれ……!」 「さすがに一生は……」と言いかけるカーヴェインを、私とフェステは睨みつけて黙らせる。 シャルロットはというと、真っ赤になって譫言のように、「一生……一生……」と呟いていた。 「さてと。それじゃあ、後は若い二人に任せて」 「うむ。わしらは退散するとしよう!」 ひたすら狼狽えるカーヴェインと、チョロインモードから復帰しないシャルロットを残し、私とフェステは開拓局を後にするのだった。