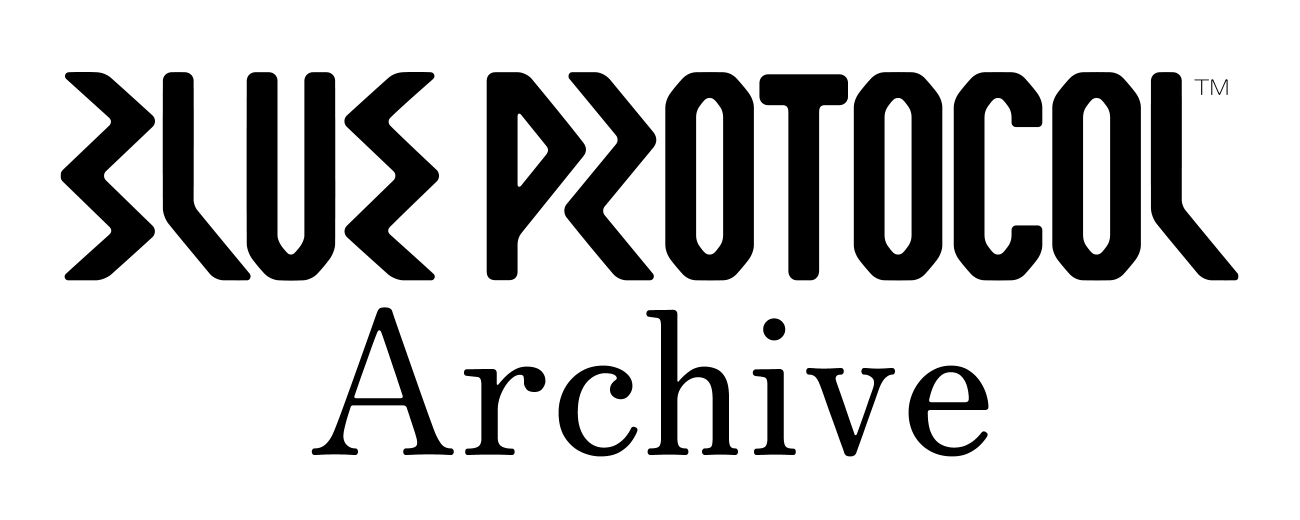命往くもの 星に来る者
uploaded by
MacCready
散文詩のような何か。サ終発表後Noteで公開してたもの。 敢えてキャラの名前は書かず、誰にでも当て嵌められるように書いてたり。
──声が聞こえたんだ。 声に応じて目覚めたら、俺は知らない場所で、見慣れない衣服を纏い、靄のような、霞がかかった頭を抱えて目を覚ました。 たまたまあの場所に訪れていた小柄な少女と出会ってなかったら、記憶がないまま一人で彷徨っていただろう。何も思い出す切欠も掴めぬまま、身を窶していたに違いない。 そうならなくてよかった、と今では思う。 知らない土地、知らない場所、そして見知らぬ人々──そんな中で俺を助けてくれた小さな少女は、その時の事を話す度やれやれと辟易めいた言葉を漏らしつつ、 「お前がここに来る前に何処で何をしてたかはワシとて知らぬが、お前はもうワシの下僕なんじゃ。ワシのためにキリキリ働けばいずれ記憶を戻るきっかけも出てこようぞ」 傍から見れば大分酷いことを言われてると思われかねないが、名前以外の全てを奪われた状態でできる事なんて他になくて。 少女──フェステには随分助けられた。 見ず知らずの俺を助けたばかりか、衣食住の環境も整えてくれた。かつ仕事の斡旋をしてくれる開拓局に口を利いてくれるジェイクを紹介してくれた事もあって、食い扶持に困る必要はない。 だから力になりたい。恩を返したい。そう思った。 いつか記憶が戻り、自分が何者なのか判別した時、俺はどうなるのか……なんて先の事は分からないけれど。 思い出したとしても、……大丈夫。 俺は彼女の傍にいよう。いつまでもずっと。 「? ……何か言ったか? 下僕?」 時折様子伺いにラルパルを訪れては、すっかり懐いている彼女の最初の下僕と呼ばれた数匹の猫とじゃれあっていたフェステが、ふいとこちらに顔を向けてきた。 「いや? 何も?」 とぼけて見せたが、多分彼女は地獄耳だ、俺がぼそっと口の端で呟いた言葉を聞いたうえで問うてるのだろう。そういう悪戯を仕掛けてはニヤニヤ笑うフェステはそこが魅力の一つで、憎めない所でもあった。 ふうん、とつまらなさそうに一瞥し、向きなおしてじゃれてる猫と再度戯れだす。ラルパルの村民はそんなフェステにかわいいわねぇ、なんて声をかける者もいるが、実際の所俺より年が上だなんて誰が信じようものか。 ありがとう、と猫なで声を発するフェステに心の中でため息を漏らしつつ、俺は草むらに寝転がった。 あの“声”はもうしばらく聴いていない。 けど……たまには自分の事も、この世界に今起きていることも忘れて居眠りに興じてもバファリアの神様は文句は垂れないだろうし、俺の主は猫と遊んでいる。下僕たる俺はそれを邪魔する理由もなければ、安穏たる時間位与えてもらっても罰は当たらないだろう。 そう心の中で結論づけ、彼は草むらで居眠りを立て始めた。 この安穏たる日常が、非日常に変わらない事を祈りつつ。