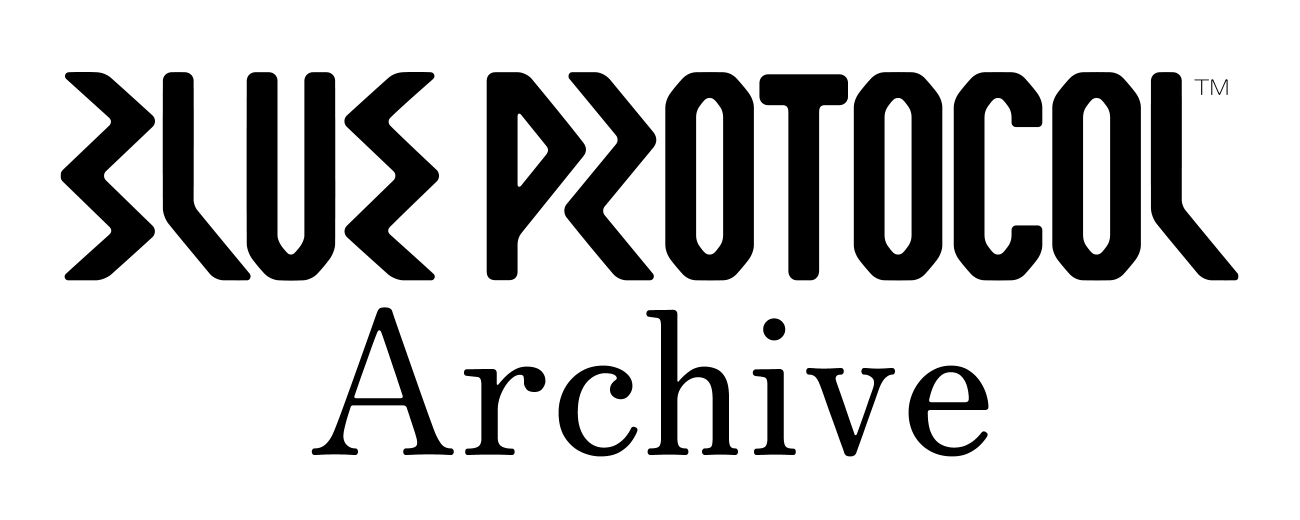If Chapter「優しい未来」
uploaded by
Skyf Lute
おたんぬ様主宰のブルプロアンソロに出させていただいた小説になります。 まだ7章実装前だったので、少し整合の取れないところもあるかと思いますが、お許しを
――カラン 「ジェイクよ、ワシらが帰ったぞ~」 「只今戻りました、ジェイクさん」 「Welcome back! お嬢さん達」 いつものように双面コイン亭に戻ったフェステ達を迎えたのは、何故かカウンターではなくテーブル席に座ったジェイクだった。 「なんじゃジェイク、サボっておるのか? まあ確かに客はおらんようじゃが…」 「No,No! 濡れ衣だぜ」 ジェイクが頭を振って無実を訴えていると、カランとドアが開いた。 「あら、フェステさんにエーリンゼさん、お久しぶりです」 「む、ミューリィか、久しいのぉ」「お久しぶりです」 ――ジェイクめ、さてはミューリィとデートじゃな。まったく隅に置けん奴じゃ。 いつの間に進展していたのやら。 「そういえば嬢ちゃん、あいつらは?」 「ん、あぁ。下僕たちは依頼の達成報告で開拓局に行っておる。もう少しすれば戻ってくるじゃろう。なんじゃ、用事でもあるのか?」 「…いや、それならいい。そんなことより荷物置いてきたらどうだ、持ちっぱなしは疲れるだろ」 「ワシらはそんなひ弱じゃないわい。…じゃがまあ、お言葉に甘えて一旦失礼しようかの」 「はい、失礼しますね」 エーリンゼがペコリと頭を下げて、二人は二階の部屋に向かう。その後ろではジェイクがミューリィに隣の席を勧める姿が。 ――あやつ、仕事せんでいいのかのう? と思わないこともなかったが、なんだかんだ真面目なジェイクであるから、問題ないのだろう。 一階に戻ってくると、先程まで閑散としていた店内には何人かの見知った客の姿があった。 「おぉ、なんだか賑やかじゃの」 「今日は何かあったでしょうか?」 心当たりも特に無いので、そう首をひねっていると、新たに二人、コイン亭に入ってきた。 「エーリンゼ様、只今戻りました」 「もどったよ、フェステ」 「おぉ下僕!」 「おかえりなさい、ティリス」 入ってきたのは、開拓局での報告を終えたティリスと下僕。 「無事、達成認定をもらってきました。報酬はこちらに」 ティリスが掲げた報酬のルーノが入った袋にフェステはついニヤリと笑ってしまう。 「のう、下僕よ……」 下僕たちなら、コイン亭のこの雰囲気について何か知っているだろうか。 そう思ってフェステが口を開きかけたその時、再びコイン亭のドアベルが鳴った。 反射的に入口に視線をやって、そこにいたのは… 「まったく、この音でさえ懐かしいったらありゃしない」 「亭主!! どうしてここに!!」 「どうしてって、おいおい、ここは俺の店だってのを忘れたのかよ?」 ニヤリと笑いながら、態とらしく肩を竦めるコイン亭亭主――公王ノルベルト。背後には、騎士団長ダンケルクや副団長ヴェロニカ、更にはヨルク、カーヴェインを引き連れており、まさしく公国首脳陣勢揃いであった。 亭主は常連たちに挨拶しながら、カウンターへ。 みな、亭主の顔を見て再会を喜んでいる様子だが、驚いているのはフェステたちだけ。どうやら常連たちは亭主の帰還を知って集まっていた様である。 「お久しぶりです、師匠とその主!」 「うむ、カーヴェインよ、久しぶりじゃな」 「最近どう? 調子は」 何気ない様子で尋ねられた言葉に、カーヴェインが顔を顰める。 「すまんな、聞くまでもないことじゃったか」 「えぇ。英雄と呼ばれるのは嬉しいですが、どうにも性に合いません。最近は式典も多くて、毎回ヘトヘトです」 「カーヴェインさんは、何と言っても邪竜リーンブルムの企みから公国を守った英雄ですから」 エーリンゼが無邪気な笑顔で「人気なのも当然です」と付け加える。 「俺はただ戦っただけで、ヨルクこそが一番の功労者だと思うんですけどね」 はにかみ気味にカーヴェインがそう謙遜する。 ヨルクは秘密裏に進めていた独自の調査から、竜族リーンブルムの、更には当時高等文官の地位にあった獣の使徒ユーゴの謀略の存在に気づいただけでなく、事件解決のための作戦立案も行い、智謀の英雄として公国内でカーヴェインに並ぶ名声を得た。 「そう卑屈になるでない。ヨルクの作戦とて、お主の戦力あってこそじゃろうて。英雄たるもの、胸を張って威張っておればよいのじゃ」 「そうだよ、カーヴェイン」 話題にされているのに気づいたからか、ヨルクが父親のダンケルクにヴェロニカを連れてやって来た。 「それにあの時、騎士団は汚染されていて、信頼できる仲間だって君くらいしか居なかった。調査だって、君の協力なくしては上手く行かなかったさ」 容赦のない言い様に、後ろでダンケルクは苦笑いだ。 思えばカーヴェインと初めて会った時も、彼はヨルクの依頼で調査をしていたのだった、とフェステたちは懐かしく思い出す。 カーヴェインはついヨルクに言い返そうとするが、ダンケルクがそれを制し、二人の肩に手を置く。 「カーヴェイン、卑下する必要はない。二人とも、我が自慢の息子だ。どちらもただ、胸を張っていればいい」 「騎士団長、はい!」「父さん…」 ――うむうむ、仲良きことは良いことじゃ、と頷くフェステ。 「あの時は貴公らにも色々と世話になった。私としてはもう少し話をしていたいところだが…」 「ダンケルク様、今は護衛任務中です。あまり公王陛下から目を離さないでください」 「だ、そうだ」 ヴェロニカは相変わらずの生真面目さである。 では失礼する、と言ってダンケルクは彼女を伴いカウンター横の壁際へ去っていった。 「のうヨルクや、息子のお主から見てどうじゃ、あの二人は」 「なかなか順調です、この間ついにデートの約束をしたとか。まぁ父さんは相変わらず鈍感ですから、デートだとは思ってないみたいですが」 他人の恋模様でニヤニヤ悪い笑みを浮かべる二人。 ――はぁ、駄目だこりゃ。 全員が心のなかでそう思っていると、コイン亭に新たな一団がやってきた。 「おじゃま、します……」 「みんなの歌姫、シャルロットが来たわよー」 「おぉ、噂通り亭主さんが! やっぱり亭主さん居てこそのコイン亭ですね!」 「コイン亭は久しぶりですしょ? 先生」 「そうですね、ミルレーネ。騒がしいのは得意ではありませんが、ここの空気は嫌いではありません」 「大勢で押しかけてしまい申し訳ありません、亭主」 リュゲリオに率いられたバファリア教にまつわる者たちである。神官長と左遷された三等神官という、何ともアンバランスな大人二人は早速、亭主の居るカウンターへ。 歌姫たちがフェステたちの所へと寄って来た。 「アインレイン、久しぶりだね!」 「うん、ヨルクも……。元気そうで良かった……」 相変わらずな幼馴染ペアは置いておくとして… 「歌姫たちや、どうじゃ調子は? 練習はよいのか?」 シャルロットたち三人は、今夜に迫る星霊祭で、去年に引き続き星霊の歌姫を務めることになっている。 「ふっふっふー、用意はバッチリよ!」 「今回は新曲も用意しました。本番を楽しみにしていてくださいね!」 「なかなか満足の行く仕上がりだから、期待してくれていいよ!」 「それは楽しみです! やはり、今回もしっかり観に行かなければですね、ティリス!」 「はい! エーリンゼ様」 主従二人は去年のステージを観ていたから、今年も楽しみで仕方がない様子である。一方フェステなどは、護衛仕事でステージを見ることはできなかったわけで。 「フェステさん達も、今年はしっかり、私達のステージ見に来てくださいね!」 「うむ、もちろんじゃとも!」「楽しみにしてる」 去年は大いに盛り上がったから、観られなかった事を密かに悔いているフェステである。当然、今年は観に行くつもりであった。 「カーヴェインも、しっかり観に来てよね! なんてったって……この歌姫シャルロットの最後のステージなんだから」 「あぁ、それはもちろん……」 そう、シャルロットは今回の星霊祭を最後にステージから退く。それはもちろん、彼女が未来にいる両親に会いに行くためで……。 「でも、きっと最後じゃないさ」 「えっ」 「君は未来に行っても歌うだろうし、それに…」 ――帰ってくるだろう? この時代に。 カーヴェインの声色には確信しかなくて、シャルロットも、そうなるだろう事をただ信じられた。 「そうね、うん。私は、お父さんとお母さんを、破滅の未来から救って、それで、帰って来る」 「その意気じゃぞシャルロット! 安心せい、何かあってもワシの下僕らが助けに行くからな」 「ちょっ「フェステ(さん)!?」」 「私も助けに行きますよ!」「もちろん、俺もだ」「オレだって行くぜ!」 エーリンゼにカーヴェイン、離れた席のジェイクも。 「みんな……ありがとう!」 溢れかけた涙を拭って、シャルロットは眩しく笑った。 しんみりした話はやめて、雑談に花を咲かせていると、また新たな客がコイン亭にやってくる。 「どうぞ、お入りください」 「ご苦労、カパクク」「ご苦労っぽ」 聞こえた声に、一番驚いたのはやはりララフォルテだろう。 「ピピマルカ様!?」「なぬっ!」「えっ!」 カパククの先導で、森の民の女王であるピピマルカ、そしてその肩に乗る原老カヴァ・アクが入店した。 「この街は良いな、実に活気に溢れている」 「ワシは水が美味しければ満足っぽ」 「ど、どうしてピピマルカ様がこちらに?」 混乱しつつ、ララフォルテはなんとか尋ねることに成功した。 「……なんだ、私が来ては行けなかったのか」 「い、いえ、そんな事はありませんが」 いつの間にかカパククが亭主から水の入ったコップを受け取っていて、それをカヴァ・アクに渡している。受け取ってカヴァ・アクは、「美味いっぽ!」それは良かった。 「ピピマルカ様はな、お前が星霊祭に出るとお聞きになってそれを観に来られたんだ」 「でも、星霊祭は……」 バファリア教の祭事で、と続けようとして、それより先にピピマルカが口を開いた。 「確かに、バファリア教会には思うところがある。が、それで毛嫌いしていても仕方あるまい。森の民の活躍を見届けるのもまた女王としての役割。それに、エーリンゼ殿には、感謝してもしきれぬ恩がある故な」 いきなりエーリンゼの名前が出てくる理由が分からず、思わずララフォルテは彼女の方へ視線を向けた。 「お節介とは思いましたが、私の方からピピマルカ様に少しお手紙を。ララフォルテさん、ピピマルカ様にも観ていただきたい、と言っていたから」 「エーリンゼさん……ありがとうございます!」 喜色で頭を下げるララフォルテと、少し照れたピピマルカを見て、エーリンゼは心の底から嬉しかった。 仲違いした同胞が、こうして仲を修復できている。きっと世界はもっと、みんなに対して優しく在れる。皆が平等に優しく受け入れられる世界だって、自分の理想だって、決して夢物語じゃない。 そう、確信できる。 コイン亭横の建物の屋根に人影があった。 「どうしたんだい、ヴォルディゲン。入らないのかい?」 「っちょ!? メルロウフかよ、ビックリさせんじゃねぇ」「口が悪いぞ、フレルベ」「エルニゲスのおっさんは黙ってろ」「お二人とも静かになさってください」 話しかけられた当人――竜王ヴォルディゲンはガヤガヤとうるさい同行者たちに呆れのため息を吐き出してから言葉を返す。 「驚かすな放浪者。お前たちも黙っていろ」 「ごめんって」 謝っているにしては軽い口調だが、彼がこういう質であることは知っているから、ヴォルディゲンはそれ以上言わなかった。 「気に病む必要はないさ、彼女たちだって、君の立場は理解していた」 「そうだろうが、感情というのはそう単純ではない」 「ははっ、その返しは僕に対して卑怯じゃないかい?」 「思ってもいないことを」 ヴォルディゲンは腰掛けていた煙突から体を起こすと、いくぞ、と言って道へ降りた。それに竜族たちも、メルロウフも続いた。 「邪魔するぞ、公王」「よっ」「失礼する」「へぇ、ここが…」 それぞれが皆らしいセリフと共に入店してきたのはヴォルディゲン率いる竜族たち。 あまりの陣容に、店内も思わず静まり返るが、そうでなかったのが若干名。 「久しぶりだな! ティリス。エーリンゼ様も、お久しぶりです」 「「フレルベ!」」 もう一組は落ち着いた様子だ。 「よっ、ヴォル。よく来たな」 「せっかくの招待、断るのも無粋だろう」 「亭主、竜王相手に何たる呼び方を……」 図太さに定評のあるフェステも驚いてしまう程の気安さでヴォルディゲンに接する亭主だが、互いに民を纏め上げる王の地位にいると思えば、ある意味で必然なのかもしれない。 普段通りの亭主の様子に、徐々に客たちも平静を取り戻していく。 「そちらに預けている同胞はどうですか?」 「よく働いてくれていて、非常に助かっています」 いつの間にか話し出しているのはヨルクとアヴニンテ。話題は始まったばかりの竜族と公国の交流だ。 先頃、グランヴィル氷界に住まう竜族たちはバーンハルト公国との国交を樹立し、長年人類の脅威であった竜族は人類の同胞として受け入れられた。 それに伴い不要となった、西バーンハルト半島一帯の対竜族防衛陣地の撤去と跡地の再開発が、竜族と公国の共同事業として行われているのである。 「特にウルガルムさんは大活躍で、この間も城壁の撤去を一人でやってしまいましたね」 「あれは体力バカですから、存分に使ってください」 智謀を得意とする二人だ、気が合うのだろうか。お互いに少し笑いながらといった様子で話している。目が笑っていないのは気の所為に違いない。 亭主と話すヴォルディゲンに、エーリンゼが横から話しかける。 「ヴォルディゲンさん、その後、お加減いかがですか?」 「ん、あぁ。シェルの影響はもう完全になくなった。感謝する、エーリンゼ殿」 アバリティアシェル計画の影響でかなり特殊な状態でアバリティア化していたヴォルディゲンの歪みを治したのは、エーリンゼの力だった。 「そうですか、それは良かった!」 ――この娘は、敵対していた筈の相手にさえ慈悲深い。それは美徳だが、同時に欠点ともなりうる。願わくは、それが欠点となることの無い世が続かんこと。 ヴォルディゲンは、酒の入ったグラスを傾けた。 「良い酒だな、公王」 フレルべは一通りティリスと話し満足したのか、カウンターで亭主に酒を要求している。 「先輩、今更ですが報酬を部屋に置いてきましょう」 「うん、そうだね」 二人は連れ立って階段を登り、ふとティリスが部屋の前で立ち止まって吹き抜けから階下を見た。 「みんな笑っています。……この景色はきっと、先輩があの時、シェルに取り込まれそうだった私の手を取ってくれたおかげです」 「……あの時は、すごくヒヤヒヤした」 笑い事じゃないのに、ティリスはくすっと笑った。 「ありがとうございます、先輩!」 いきなり駆け出して部屋に入ったティリスに、呆気に取られた。 ――これは、君の望んだ未来かい? 希望の落とし子。 「えぇ」 ――そうか、それは良かった。 私は歩く、この先も、ミライへ。