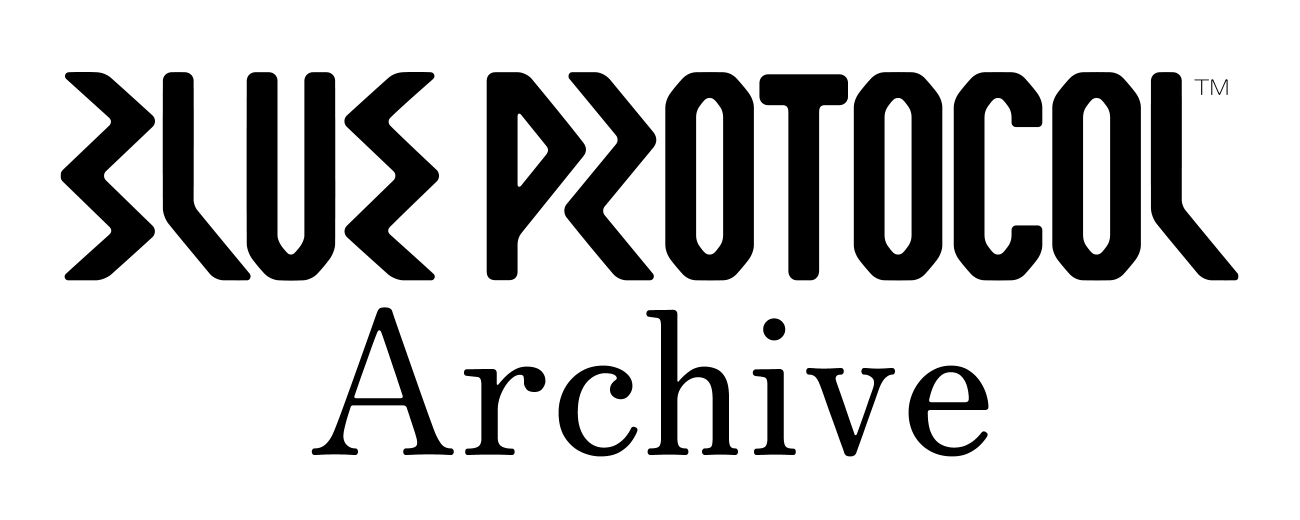フェステ、ギター弾くってよ
uploaded by
じじょう
BPアンソロ2に載せてもらったやつ。タイトルでギター弾くと言っておきながらフェステがギターを弾くシーンは1ミリもない
『アステルリーズ夏の武闘大会、開催決定! 武器ありイマジンありの大舞台で勝利を掴め! 優勝者には賞金として百万ルーノを贈呈! 挑戦者絶賛募集中!』 「百、万……じゃとぉ!?」 開拓局の掲示板に張り出されたその知らせを見た亜人の少女は、目玉を飛び出させるほどに驚く。そして既に勝ちを確信したかのように百万ルーノの使い道を考えながら、居候先である双面コイン亭へ急ぎ足で向かった。 「おい下僕! コレに出るぞ!」 バン!と勢いよくコイン亭二階の扉を開けると、少女は開口一番に威勢のいい声で部屋の主に告げる。 下僕、と呼ばれた年齢も性別も判別しづらいその者は、磨いていた剣をベッドにそっと置いてから亜人の少女の方を向いた。 「なにフェステ、開拓局でまた変な依頼でも見つけたの?」 亜人の少女の名はフェステというらしい。 「またとはなんじゃ! それに依頼でもないわ!見よこれを!」 フェステは拝借してきた張り紙をずいっと下僕に向かって突き出す。その張り紙に大きく書かれた『百万』の文字を見ると、下僕はフェステの意図をなんとなく察し、またか、といった表情を浮かべた。 「私にこれに出て賞金をかっさらってこい、と」 「そうじゃ! 百万じゃぞ!? 借金がチャラになったとはいえ、金なぞあればあるほどいいからのう!」 「でもこれ、私出れないよ?」 「なんでじゃ、別に暇であろうに」 「いやほらここ」 下僕は張り紙の下部の詳細欄を指差す。 そこには── 「──下僕だけ名指しで出場禁止になっとる……」 参加者の資格は問われていない中、下僕だけ名指しで出場を禁止されていた。理由は、まあ、言わずとも分かるだろう。 「まぁ私ってばヴォルディゲンも倒しちゃったじゃん? そんな人間がこの大会に出たらゲームブレイカーになっちゃうもんね〜。いや〜出たかったな〜、無双したかったな〜!」 出禁となった本人が嬉しそうに言ったが。 そう、フェステが勝ちを確信していたのはこの下僕の存在があるからだ。この(外見上は)ただの少女のフェステと一応の主従関係を結んでいる下僕だが、その実力は人類最強と謳われる騎士団長や、竜族の長である竜王を打ち倒すほどのものなのだ。 「殿堂入り扱いで浮かれておるなこいつ」 ニヤニヤする下僕に冷めた視線を送るフェステだが、しかし頼みの綱である下僕の出場が叶わないことを理解すると、今度は頭を悩ませる。 「下僕が出れないとなるとつまり、ワシはこの百万を諦めるしかないのか……?」 「フェステが出ればいいじゃん」 「バカ抜かせい! ワシが可憐でか弱い美少女フェステちゃんであることを忘れてもらっては困るぞ! 戦闘などからっきしじゃい」 そう言って服の袖をたくし上げ、白く細い二の腕を下僕に見せる。筋肥大とは無縁そうな上腕二頭筋がほんの少しだけ縮み、力こぶ……未満の何かを演出した。 「そこはまぁ、殿堂入りしたこの私が手取り足取り角取り教えてあげるよ。開催まで二週間もあれば形にはなるでしょ」 「う、う〜ん……まぁちと不安ではあるが、この機会を逃す手はない、か……」 少し躊躇いはしたものの、フェステは意を決する。 「よし! その提案、乗った! じゃがワシが出るからには賞金は全部ワシのものじゃからな!」 「いいよ、私はダンジョン周回で出た武器売りまくってルーノ有り余ってるし」 「ブルジョワジーめ!」 * 「じゃあまずは武器から選んでいこうか」 二週間あるとはいえ、しかし二週間しかないとも言える。戦闘経験ほぼゼロの人間を鍛えるには短すぎると言っていいくらいだ。 であればのんびりしている時間はない、ということで二人はアステルリーズを飛び出し、橋を渡ってすぐの海鳴りの平原に来ていた。 「とりあえず全武器種を持ってきたから試してみようか。まずは私のオススメの剣盾から」 色々な武器を詰められたことで破裂寸前の風船のようになったバッグの中から、一対の剣と盾を取り出し、フェステに手渡す。 「確かに冒険者といえばコレ、といった感じじゃな。どれ……」 渡された剣盾を持ったフェステだが、下僕が手を離した瞬間、腕をぷるぷると震えさせる。なんとか持ち上げようと踏ん張るも、十秒と保たず武器を地面に落としてしまった。 「いや重い! 薄々気づいてはおったがこんなん片手で持てるかぁ!」 下僕愛用の剣盾は、フェステには少々、というか重々、手に余るようだった。 ズドン、とフェステが手から離した剣を改めて見てみると、確かに片手剣と呼ぶには刀身は分厚く広く、そのクセして柄は片手剣らしい長さときた。フェステの細い腕では確かに持ち上げることさえ困難だろう。 「そりゃあ自分より大きいモンスターを斬るんだから……ある程度の重さはあるよ」 「ある程度て。ともかく、二週間あってもこれを片手で持てる気はせんな……ワシでも使えそうな武器はないのか」 剣盾を下僕に押し付け、フェステは次の武器を要求する。 「重くて無理なら杖とかどう? 今のほど重くないし、柄も長いから両手で持てるし」 下僕は取り出した杖をフェステに渡す。今度はフェステの膂力でも十分扱えるようで、上部についた装飾の下を片手で握り、ブンブンと振り回す。 「うむ、これくらいなら全然使えそうじゃ!」 「ならよかった。そしたら杖、スペルキャスターはもう簡単だよ。こうやって、敵の後ろに回って屈伸しまくるだけだから」 予備の杖を持った下僕は、近くにある練習用のかかしの背後からサンダーマインを連発する。バリバリという轟音にさえ目を瞑れば、たしかに屈伸、というかスクワットをしているだけだ。が。 「あのなぁ下僕、一つ、一般常識というやつを教えてやろう。そんな芸当ができるのはほぼ無尽蔵の生体エングラムを持つ下僕だけじゃ。ワシのように普通の人間がそれをやったら秒でぶっ倒れてしまうわ」 「文句の多い主人め」 「下僕は自分の強さというものを理解せい!」 杖でぽかっと下僕の頭を叩くフェステ。大して痛くなかったようで、下僕は表情一つ変えずにそのまま受けた。 そういうところじゃ、と苦言を呈しかけるフェステだが、言っても仕方のないことか、と諦めて次の武器を催促した。 「重いモノは無理、エングラムもそんなに使えない……となるともうこれしかないや」 ガサゴソとバッグの中を漁り、下僕は一つの武器──と言っていいのかも分からないが──を取り出す。 取り出したのは、特徴的なボディから長いネックが伸び、その上に何本かの弦を張った──ギターだ。 「武器じゃなくて楽器になってしもうた」 「失礼だな、これもれっきとした武器だよ」 ストラップに肩を通した下僕は、弦に挟んでおいたピックを持つ。そして軽く辺りを見渡し、少し離れたところにいるウリボに目をつけると、その足元にアンプを召喚し、ギターの弦を勢いよく弾く。 するとまるで突風《カマイタチ》にでも斬られたかのようにウリボの体表に大きな切り傷が刻まれ、そのまま倒れた。 「こんな感じでね。アンプ召喚の時だけエングラムを使うけど……まぁ一回召喚したアンプを蹴り飛ばして動かせば再利用できるでしょ。どう?」 デモンストレーションを見せた下僕は、振り返りフェステに視線を送る。 そのフェステはというと── 「──いいのうそれ! こう、ロックな感じとか、スタイリッシュな感じとか、まさにワシにぴったりじゃ!」 下僕の心配などどこ吹く風といった様子でギターに心を奪われていた。 「気に入ってもらえたようで何より。じゃ、さっそく特訓を始めようか!」 「うむ! バッチコーイ!」 * 時は流れ、大会当日。 「ヘイガールズ! 奇遇だな」 「ぬっ、ジェイク。お主も出るのか」 会場である闘技場前で受付を済ませていた二人は、トップオブトップ冒険者にしてコイン亭現店主のジェイクと鉢合わせた。 「オフコース! そういやあんたは出場禁止になっていたと思うが……まさか、フェステが出るのか!?」 「おうよ! この二週間下僕のスパルタ訓練を耐え抜いたワシは、もうお主の知る可憐でか弱いプリティーフェステちゃんではない……!」 フェステは包帯でぐるぐる巻きになった腕をジェイクに見せつける。いじめ抜かれついに筋肥大と邂逅した上腕二頭筋が、包帯を内から少しだけ持ち上げた。 「じゃ、私はコイン亭でエーリンゼと留守番してるよ」 「エーリンゼ……ハッ!待った下僕!」 下僕のセリフから何かを思いついたのか、フェステは会話を聞かれぬよう、下僕をジェイクから少し離れた場所に誘導する。 「アレを貸してくれ」 「……いいけど、多分使いこなせないよ」 「いいから貸せい!」 「はいはい。それじゃ、二人ともがんばってね」 フェステに何かを手渡すと、下僕は大会に臨む二人を見送り、一人でコイン亭へと帰っていった。 三時間後。 「負けた〜〜〜〜〜〜!」 ボロボロになったフェステがジェイクにおんぶされながら帰ってきた。 「おかえりなさいフェステさん! ジェイクさん! 二人ともお疲れ様でした!」パリン。 「ん、おかえり。やっぱアレ難しかったでしょ」 帰ってきた二人に声をかけたのは下僕と、皿を洗っている、そう一応洗ってはいる、コイン亭でバイト中のエーリンゼだ。 「決勝までは順調だったのに! こやつに負けてしもうたわ!」 「鉄壁のアインリンゼ戦法も再使用のタイミングをミスしたら負けちまうのさ。だが、たった二週間であそこまで強くなったのは素直にリスペクトだぜ」 大会直前にフェステが下僕から借りたのはアインレインとエーリンゼのバトルイマジンだったようだ。しかし付け焼き刃のそれもジェイクには通用しなかったらしい。 「キィーッ! 同情するならその賞金ワシにもよこせぇい!」 「ハハ、ソーリー! これはディッシュの購入に充てなきゃならないんでね」 「まぁまぁフェステさん、お金ならまたみんなで冒険して稼げばいいじゃないですか!」パリン。 「……だからといって何枚でも割っていいわけではないんだがね、エーリンゼさん」 「こ、これは決して故意では!」パリン。 漫才のようなやり取りをするエーリンゼとジェイクを見て吹っ切れたのか、フェステは軽く笑い声を上げた。 「ははっ、まぁ強くなれただけでもよしとしようかのう。これで下僕の負担も少しは減らせるじゃろう」 「えっ」 「ほれ、いつも戦闘は下僕に任せっきりじゃろう? じゃがワシも強くなったことだし、たまに……そう、たまーにくらいなら手伝ってもよいかなーと……」 言いながらこっ恥ずかしくなったのか、フェステは下僕から顔を逸らした。 「いやフェステちっこくて視界に入らないから蹴っちゃいそうだし、いつも通り後ろでヤジ飛ばしてくれてればいいよ」 「下僕お前外に出ろワシのギターで脳みそシェイクしてやる!」