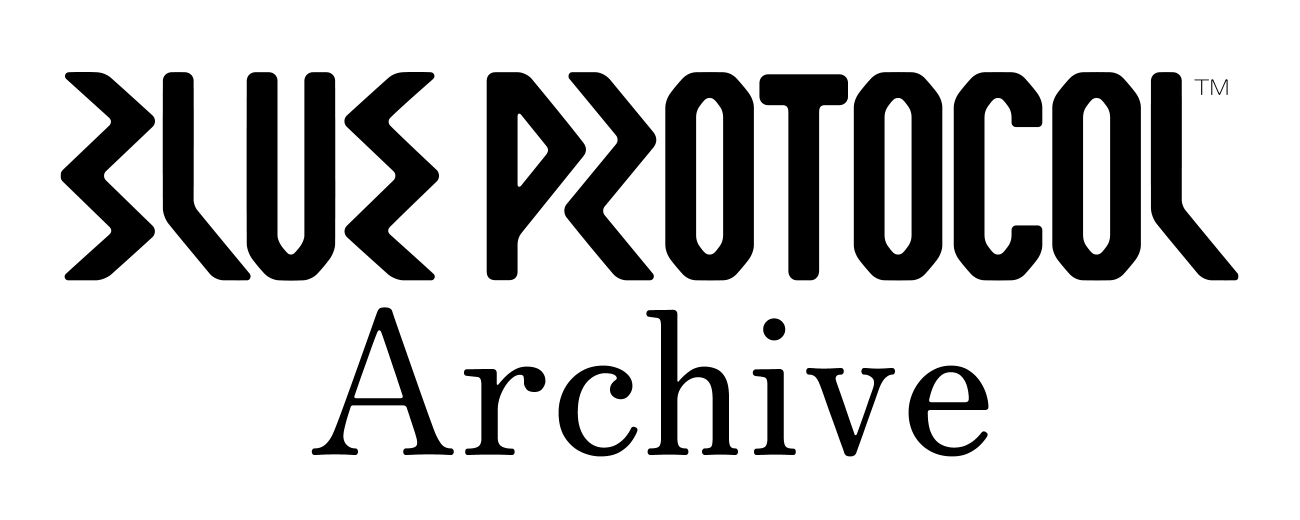ターフに託して散った夢
uploaded by
サニーブライアン
おたんぬ様主宰のMemory of BLUEPROTOCOL 3に寄稿した作品です
「はー。平和が素晴らしい……」 エーリンゼとティリスの仲良し主従はお出掛け中。フェステは朝から姿が見えない。 そんなわけで、私は自室でゴロゴロして過ごしていた。インドアライフ万歳。 「おーい、下僕よ! ビッグニュースじゃ、ビッグニュース!」 階下から大声で私を呼ぶ声が聞こえた。同時に、バタバタと階段を駆け上がってくる音も。さようなら、私の平穏。 「おい、下僕よ! 何をダラけておるのじゃ!」 ドアを開け放って開口一番、フェステはそう宣った。 「……いったい、何の騒ぎ?」 「良いから、これを見るのじゃ!」 そう言ってフェステが差し出してきたのは、アステルリーズ商工会のチラシだった。 「えーっと、なになに……競ボアレース?」 競ボア? ボアを競わせるという意味なんだろうか。ちょっと意味が分からないかな。 説明を求めるようにフェステに目を向けると、ニンマリとした笑みを浮かべ、滔々と話し始めた。 彼女曰く、人に懐くようにウリボの頃から育てたボアを競走させて、どのボアが一着になるのかを予想するゲームなのだという。 見事一着になったボアを的中させれば、オッズに応じた配当が得られるらしい。 「これで一発デカイ山を当てれば、労せず大金持ちじゃ!」 「……はぁ」 そう息巻くフェステに、私は溜息しか出なかった。 「むっ。なんじゃ、その呆れたような溜息は」 「そりゃあ、溜息だって出るよ。ギャンブルで一攫千金だなんてさー」 だいたい、ギャンブルなんてものは、胴元だけが儲かるように出来ているんだし。 のめり込んで大損して、借金を増やすだけの未来が、手に取るようにわかるよ。 「ワシに任せておくのじゃ! 行くぞ、下僕よ!」 「ええー……」 部屋に引き籠っていたいところだけど、フェステ一人で行かせたら、破産してしまうかもしれない。 私は仕方なく付き合うことにした。 フェステに引っ張られるようにして、私は競技場までやってきた。 「うっわ……。凄い熱気」 「う、うむ。大した盛況ぶりだの……」 あまりの人出の多さに、私達は圧倒された。 アステルリーズの全市民が集まっているんじゃないだろうか。 それだけ、注目度が高いという事でもあるんだろう。 「とりあえず、投票券を買おうかの」 「投票券?」 「うむ。投票券にボアの名前が書かれておってな、そのボアが勝てば配当金がもらえる仕組みというわけじゃ!」 「なるほどねー」 「なんじゃ、その気の無い返事は」 そんなこと言われてもねえ。そもそも全然乗り気じゃないし。 「んじゃあ、適当にこれで良いや」 「では、ワシはこやつにするかのう!」 私達はあまり深く考えず、フィーリングで投票券とやらを購入した。そして……。 「か、勝った……」 「うおー! 負けたぁー! 何故じゃー!」 私が何も考えずに買ったボアの投票券が勝ってしまった。 しかも、それが万ボア券? とかいうやつだったらしく、とんでもない額の配当金が払い戻されたのだ。 やばい。これ、結構面白いかも。 「ええい! 次、次じゃ、下僕! 今度は、ワシが勝つのじゃ!」 「よーっし! 次も当ててやるよー!」 会場の熱気と、地面を蹴立てて怒涛のように走るボアの勢いに飲まれたのか、私とフェステは、次のレースもその次のレースもと、結局、全レースが終わるまで、投票券を買い続けたのだった。 * 「……で、全財産擦ったってわけか」 「は、はい……」 「う、うむ……」 夕暮れ時のコイン亭。 私とフェステは、腕組みする親父さんを前に、神妙な面持ちで床に正座していた。 「まったく。フェステはともかく、お前さんまで何をやってるんだ」 「め、面目次第もありません……」 親父さんは、怒っているというよりも、呆れ果てているという感じに見えた。 「おい、亭主! ワシはともかくとは、どういう意味じゃ!」 親父さんは、フンと鼻を鳴らしただけで、フェステの抗議を無視した。 「ギャンブルなんてものは、胴元だけが儲かる仕組みになってんだ。それで稼ごうなんて魂胆が、そもそも間違っている」 はい。全くその通りです。私も、朝の時点ではそう思ってたんです。 「そ、それで、親父さん。大変申し上げにくい事なんですが……」 私がおずおずと申し上げるように言うと、親父さんにギロリと睨まれた。 「今月の宿代も擦っちまったんだろ?」 「ご、ご明察の通りです……」 「ツケは認めん!」 「ええっ!?」 「なんじゃとおお!?」 私とフェステは悲鳴を上げた。 「働かざる者、食うべからずだ。そういうわけで、宿代分は、きっちり働いてもらうぞ?」 そう言って親父さんは、意地悪そうに口の端を吊り上げるのだった。 * 「「い、いらっしゃいませ~」」 来店を告げるカウベルが鳴り、私とフェステは来客に向かって、ぎこちない笑顔を浮かべる。 「二人共、どうしたんですか、その恰好は」 「まあ! 可愛らしいお洋服ですわね!」 やってきたのは、エーリンゼとティリスだった。 二人が驚くのも無理はない。 なにせ、私とフェステは、給仕用のメイド服に身を包んでいるからだ。 「いったい何があったんですか、先輩」 「いやあ、実はね……」 ティリス相手に隠し通せるわけもないので、私は素直に事情を説明した。 「フェステさんはともかく、先輩まで……」 親父さんと全く同じ事を言われてしまった。 「それにしても、素敵なお洋服ですわね。わたくしも着てみたいですわ!」 「エーリンゼ様! この衣服は、エーリンゼ様のような高貴な方のお召しになるものでは……」 「それはそうと、フェステ」 そんな主従のやり取りを横目に、私はフェステに小声で話しかけた。 「このメイド服、サイズぴったりなんだけど……」 「うむ。どうやら、亭主がジェイクから借りたらしいぞ」 「ジェ、ジェイクさんから?」 フェステの話では、ジェイクさんは様々なサイズの女性用の衣装を所有しているらしい。 さすがはトップオブトップ。実にいいご趣味をしていらっしゃる。 「ミューリィには、一言忠告したほうが良さそうじゃの」 「だね」 そんなことを話していると、カウベルが鳴り、新たな来客があった。 「おい、そこの二人! 遊んでないで、きちんと接客せんか!」 「「は、は~い、只今~」」 いそいそと接客に向かう私達を、エーリンゼがキラキラとした目で見つめている。 そんなにこのメイド服が気に入ったのかな。 彼女の希望は、意外な形で叶うことになるんだけど、それはまた別の話だ。